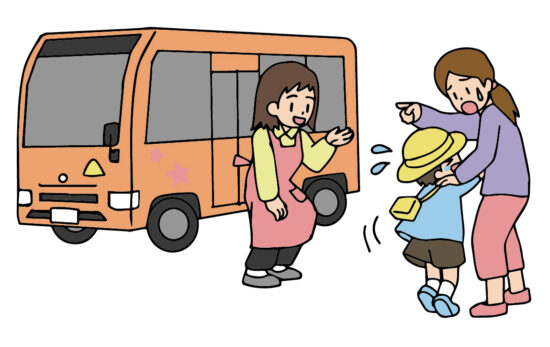登園時、先生にバトンタッチして帰る時、パパに預けて買い物に出る時など、泣いてしまってどうにもならない子供に悩む親御さんは多いですよね。
我が家の息子も、登園時に1時間以上泣きわめき続けたり、パパと二人の留守番ができなかったりと、なかなか毎日大変でした。
まだまだ完全に落ち着いたわけではありませんが、試行錯誤して取り組んだ工夫や対応を紹介したいと思います。
母子分離不安とは?
母子分離不安とは、「ママと離れるということに強い不安感や恐怖心を抱く状態」で、程度の差はありますが、1歳前後の小さい子供によくある反応。
多くのお子さんは、成長とともに落ち着いていきます。
ただ、成長過程で誰にでも見られる母子分離不安ですが、中には幼稚園行くようになっても小学校に入学しても落ち着かない、どうしたらいいんだろうってお子さんがいらっしゃるのも事実。
我が家の息子は幼稚園入園で一気に悪化したタイプです。
私は、息子が小学校に入学しても、2年生3年生になっても登下校の送迎が必須な状態が続いて、初めて母子分離不安という状態を知りました。
我が家で実践した工夫
私から離れられない状態が周りのお子さんと比べてかなりひどい状態でも、正直、私の中ではそれも息子の個性だと思っていたので、特に気にしてはいませんでした。
今では、息子の状態は母子分離不安という状態で、幼稚園入園がきっかけで悪化したということはわかります。
でも、当時は「母子分離不安」という名前すら知らない状態。
そんな中で実践していた工夫や対策を紹介します。
無理に引き離さない
まず一番に、絶対無理に引き離さないということを決めていました。
我が家の息子は、幸い家を出る時はスムーズなことが多かったです。
母が一緒だから。
自転車置き場や玄関まで来たら「ママと離れるのイヤ」が始まります。
基本的には、自分が納得して教室に入るまでは見守っていました。
自分で納得して機嫌よく離れると、ほぼ途中で園から電話がかかってくることもありません。
たまに先生がおんぶして連れて行ってくれたり、お手伝いを与えて連れて行ってくれたりしましたが、1時間以上泣きわめいて先生方もお手上げで、最終連れて帰るということも一度や二度ではありませんでした。
登園時間を守るよりも、息子のタイミングが最優先です。
安心できる約束をする
「寝ている時でも絶対に一人置いて外に出ない」「帰りたくなったらいつでもお迎えに行く」「ママはいつでもおうちにいるよ」など、息子が安心できるような約束を頻繁に口に出していました。
園でも小学校でも、本人が、もうどうやってもこれ以上がんばれないと先生に申告してきた時は、いつでも迎えに行くので電話をくださいと伝えています。
今でも。
そして、ちょっとした買い物であっても、息子と離れてる間に外出する予定がある時は、バイバイする前に話すことも約束しました。
安心グッズを持たせる
私がその時持っているハンドタオルやカギに付けてるキーホルダー、冬なら手袋など、それをお守りとして持っていくこともあります。
モノ作りが好きな息子を見て、「自分で作った作品をお守りとして持ってきてもいいよ」と言ってくださった先生にも感謝です。
正門で校長先生が作品の写真をいつも撮ってくださっていたので、息子はそれが楽しみで嬉しかったと言っていました。
登園、登校が楽しくなる工夫をする
登園、登校の時点で渋る時は、普段通らない道を通ったり、あえて反対方向に行ってみたり、虫取りをしたりなど、寄り道もたくさんしました。
結局そのまま帰ってきてしまうこともありましたが、寄り道で見つけたきれいな石や葉っぱなどを先生に見せたいからと張り切って行くことも。
息子の好きなおやつを準備しておく約束や、帰りに公園や買い物に行く約束、DVDを借りて映画タイムをする約束など、自分からも提案してくるようになりました。
スキンシップとお話を大切にする
我が家は、スキンシップと話をすることをとても大事にしています。
大人も子供も、ハグでストレスは軽減するし、何事も話さないと伝わらないからです。
ちっちゃい頃に比べたら抱っこしたりくっついてる間に寝落ちということも少なくなりましたが、ストレスが抱えきれなくなったら、ごはんもお風呂も後回しで息子の気が済むまでぎゅータイム。
未だに「ママと離れてないといけない時間がストレス」だと言うので、最終時間は決めつつ、ただただくっついてお話をする時間を大事にしています。
お話も、息子が小さい間は本人がどこまで納得できていたのかはわかりません。
それでもどうしたいのか、どうしてほしいのかをその都度たくさん話をするということはずっと続けてきています。
一緒に何かをする時間を作る
一人でだいたいのことができるようになった今でも、一緒に何かをする時間を意識して作っています。
モノづくりやお手伝い、宿題や勉強、ゲームなど、「何か」は本当に何でもいいのです。
一緒におやつを食べる、一緒にテレビを見る、一緒に本を読むなど。
ただただ「一緒に何かをしている」ということが大事なのです。
先生からの提案
小2の時に一度、担任や保健の先生など数人の先生方が、息子への接し方について悩んでるとおっしゃって、発達障害のテストを受けてみませんか?と提案されたことがあります。
その子供にどういう傾向があるかわかるだけで、対応もしやすくなるのでどうですかとおっしゃってくださいましたが、お断りして、他の子どもと同じように接してくださいとお願いしました。
腫れ物に触るような対応ではなく、怒らないといけないところは泣こうが喚こうが怒ってください、と。
それで結果どうにもならなかったら電話ください、と。
その後も先生に恵まれ、学校が嫌いだとは言うものの、不登校とは無縁の生活をしています。
母が常におうちにいる、いつでも帰れるという状態がすごく安心なんだそうです。
今自分が学校にいること以外に気が逸れないので、純粋に学校生活が楽しめる、と。
そう言われているので、息子が必要ないというまでは、私も在宅ワーカーでがんばろうと思います。
結果と今の様子
3歳の幼稚園入園から4年生の現在まで、毎日何かしらの対応、対策、工夫をしてきました。
結果、4年生の春、ゴールデンウィーク前くらいに急に一人で登下校できるようになりました。
きっかけは小2の時の担任の先生と久々に話したことだそうですが、「明日から一人で行く。お迎えもいらない」と。
徐々に、ではなくほんとに急に「明日から」でした。
時々、朝怒られたことで気持ちの立て直しができず、送っていくことはありますが。
そして、1~2分ですが、ゴミ出しの間もお留守番ができるようになりました。
それ以外は、本人曰くまだまだ無理だそうです。
まとめ
母子分離不安と聞くと大丈夫かな、と不安になるかもしれませんが、小さいお子さんには珍しくないことです。
無理に直そうとせず、叱ったりせず、安心感を与えてあげてください。
我が家の場合は、徐々に落ち着いてきたという感じはありません。
ある日突然3割くらい落ち着いた感じです。
高学年になり、修学旅行は行かないって言ってることなど気になるところはありますが、遠足は楽しんで行けてるし、息子のペースとタイミングに任せようと思っています。
お子さんの母子分離不安で悩んでるママたちへ、少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。